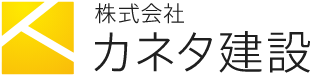釜沢用水路工事⑥「総集編」
こんにちは、土木部の神喰です。
カネタ建設には地域の土木工事を行っている土木部があります。
もっと皆さんに土木の仕事を知っていただきたいという思いで、土木部の日常や土木工事のお話をブログでご紹介していきます。
今回は、これまで紹介してきた釜沢用水路工事の総集編になります。紹介する内容は、過去のブログで詳しく紹介されているのでそちらも見てみてください。


最初のブログで紹介したのは、現場に行くための道に敷鉄板とロードマットを設置して重機が行き来しても道を傷めないようにする作業です。
この作業でつくった道は、工事の最初から最後までで一番つかう場所になります。
この道が工事の途中で通れなくなったりしてしまったらそれを直すためにまた作業をする事になるのでこの段階でしっかりつくっておく事がその後の作業にも影響してくると思いました。


この延長線で実際に作業するところの道つけの作業も紹介しました。
この道は、作業を進めていく中でベンチフリュームが設置され水路になる場所です。
水路になる場所ということは、作業が始まれば頻繁に使用する道になるのでここの道つけも大事な作業の一つだと思いました。
道幅を確保するために木を伐採したりしたので土に木の根が混ざって後の埋戻しの作業時に根っこがたくさん出てきて大変な場所がありました。


道が完成するころに合わせて水路をつくるための材料も搬入されました。
二枚の写真の材料は、水路をつくるために使用する材料です。
ベンチフリュームとそれにかかる蓋は、どちらもコンクリートでできた材料です。



材料が設置されていく過程ではいろんな作業があり、材料を設置するために決まった深さと幅で土を掘ります。
この時に、土を深く掘りすぎたり逆に浅く掘ってしまうと次の作業の基礎砕石を敷き均す時に、いっぱい砕石が必要になったり敷き均す前に削ったりしないといけなくなります。
次に基礎砕石の敷均しでは、必要な厚みと幅を確保し、敷き均した後は転圧締め固めを行います。
この土を掘って基礎砕石を完成させるまでがしっかりできていなければ材料の設置がうまくいかなくなってしまうのでこの見えなくなってしまう下の部分をつくるのが意外にも大事な作業になると改めて実感できました。
この基礎となる部分が完成したらいよいよ材料のベンチフリュームの出番。重機で吊り上げて設置していきます。
位置の微調整は人力で行い、設置するときはベンチフリュームを支える人と重機のオペレーターとの意思疎通が大事なので合図と声で指示を出しての作業が必要です。
設置が終わったら埋戻し作業。脇を土砂と砂利で埋め戻し、埋戻しが終わったらベンチフリュームに蓋をかけます。


今回は、総集編ということで過去にブログで紹介した内容を振り返ってみました。
この工事での一通りの作業を通してみて、工事前は、地面に溝を掘った所に水が流れているだけの用水路でした。
工事が終わってから撮影した写真と見比べてみると用水路の通っている場所はほぼ同じだけどベンチフリュームが入ったことで雰囲気がガラッと変わったと思います。
工事が進んでいくにつれ出来上がっていく用水路をみると図面のモノが現地に形になっていくのが実感できました。
また実際に作業をしていく中で機械や道具の使い方を向上させられたのかなと思いました。
またこの工事では、ブログに使っている写真にも写っている電子小黒板(写真内の緑色の黒板)というのを使用しての作業でした。
使い方ではまだまだ不慣れな所がありましたが基本的な機能は活かせたのかなと思っています。
こんな感じで新しい技術にも取り組みながら工事を完了させられたのが一番よかったのかなと思います。
では、次回の土木ブログもお楽しみに。
神喰